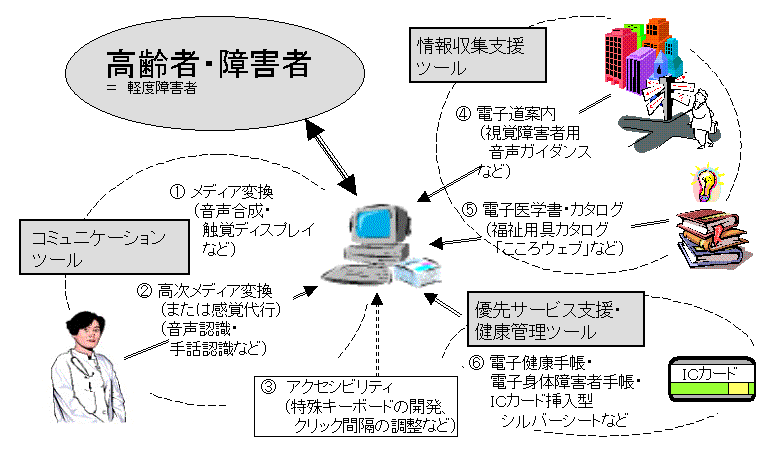
�@���H�w�A���Ȃ킿����E�`�B�Z�p�ƃo���A�t���[�Ȑ����̊Ԃɂ͈ȉ��̂悤�ȂU�̊ւ���������ƍl���Ă��܂��B
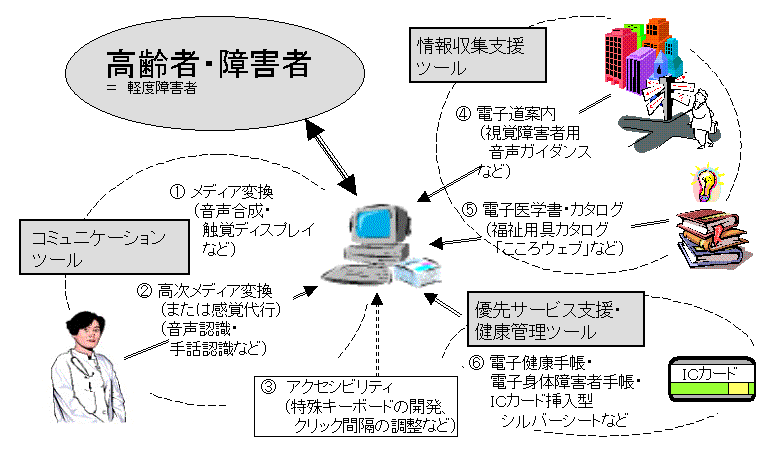
�}�D���H�w�ƃo���A�t���[�̂U��ނ̊ւ���
���F�@�}���̍��ږ����N���b�N����ƁA�}�̉��ɂ���Y���̐������̂Ƃ���Ɉړ��ł��܂��B
�@�����Łu��r�I��̃��f�B�A�ϊ��v�ƌ����Ă���̂́A�����ň����Ώۂ����ɓd�q�I�ȏ��ł���A���́u�����̃��f�B�A�ϊ��v�̂悤�ɃA�i���O�����f�B�W�^�����ɕϊ�����K�v���Ȃ�����ł��B���f�B�A�ϊ��Z�p�ɂ���ēd�q�I�ȏ��̕\���`����ς��邱�ƂŎ�Ɏ��o��m�\�ɏ�Q������l�̖��ɗ��Ă邱�Ƃ��ł��܂��B
�@��r�I��̃��f�B�A�ϊ��Z�p�Ƃ��āA����������_���f�B�X�v���C�͎��o��Q�҂��R���s���[�^���g����ŕK�{�̋Z�p�ł���A�L���g���Ă��܂��B���̑��ɁA�_���v�����^��G�o�f�B�X�v���C�Ȃǂ�����܂����A�����̋@��͌��i�K�ł͂܂����Ȃ荂�z�Ȃ��߁A�L�����y����ɂ͎����Ă��܂���B
�@���������̂悤�Ɋ������ꂽ�Ǝv���Ă���Z�p�ł��A���ۂɎ��o��Q�҂����p����Ɛ��X�̏�ǂɍs��������܂��B�Ⴆ�A���R���s���[�^��Ђ��J�����������ǂݏグ�@�\�t���u���E�U�ł��ڂɗ]�錇�ׂ�����܂��B���u���E�U�Ńz�[���y�[�W�̃L�[���[�h�����p�ɓ��͂����������m�F����ہA�u�Ă傤�̂����v�Ɠǂ܂�銿��������܂��B���͂���́u��v�̂��ƂŁA�J���҂��u�V��̈�v�Ǝw�肵�����̂����������\�t�g�̓ǂݎ����t�^�̌��ʁA�u�Ă傤�̂����v�Ɠǂ܂�Ă�����̂Ɛ�������܂��B
(1) �ʏ튿���̗p��Ƃ��Ă͑ΏۂƂȂ銿�����n��̐擪�ɂ�����̂�p����̂��]�܂����̂ɂ�������Ă��Ȃ��_�A
�����
(2) ���������\�t�g�̏����̌��ʂǂ���������邩���m�F���Ă��Ȃ��_
����A����͋ɂ߂ď����I�~�X�ƌ��킴��܂��A���Ђ̓R���s���[�^�ƊE�ł��A�N�Z�V�r���e�B��ɐϋɓI�Ɏ��g��ł���Ă����ƂȂ̂ŁA���Ђ��J����������ƂЂǂ���肪������̂����m��܂���B
�@�_���v�����^��G�o�f�B�X�v���C�̒ቿ�i�������o��Q�҂ɂ͋ɂ߂đ傫�ȈӖ��������Ă��܂��B�Ⴆ�Ύ��o��Q�҂��n�}�����悤�Ƃ���ꍇ�A�ʒu�W�����ʂŕ\�����u�G�n�}�v���K�v�ɂȂ�܂����A�_���v�����^�������Ȃ��߁A�u�G�n�}�v������Ƃ���͋ɂ߂Č����Ă��܂��B��ʂ̎��o��Q�҂̉ƒ�ɂ����E�n�}��s���{���E�s�������邢�͒����̒n�}���ȒP�Ɂu�G�n�}�v�Ŕz�z�ł���悤�ɂȂ�Ύ��o��Q�҂ɂƂ��Ēm���̕����i�i�ɍL������̂ƍl�����܂��B
(2) �����̃��f�B�A�ϊ��Z�p�i���o��s�j�@
�@�R���s���[�^���g���ĉ����F�����b�F�����ł�����A�ǂ�قǕ֗����낤�Ǝv���l�������Ǝv���܂��B����̓A�i���O�I�Ȏ��o�⒮�o�̏��𑼂̕\���`���ɕϊ�����̂ŁA����Ӗ��Łu���o��s�v�ƌ����Ă��ǂ��Ǝv���܂��B
�@�����F���͌��݂��Ȃ��ʉ����Ă��Ă���A�������̓��[�v���͂P���~�ȉ��ōw�����邱�Ƃ��ł��܂��B�����A���݂̉������͂͌����̃}�C�N���t�H������s���Ă���A�b���l�������ɂ�����A���ɎG�����������肵���ꍇ�A�K�������\���Ȑ��\�������܂���B�܂��A�������̓��[�v���́u�������t�v�𒆐S�ɂ��Ă��邽�߂ɁA�ӂ����\���������u�b�����t�v�����ׂĐ��m�ɔF�����邱�Ƃ͂ł��܂���B���݃}�C�N���t�H�����痣�ꂽ�l�̐���F�����邽�߂ɂ��낢��Ȍ������s���Ă��܂����A��肪���������܂łɂ͂܂����炭���Ԃ������肻���ł��B
�@����A��b�F���̌������s���Ă��܂����A�u�낤�҂̎�b�v�ɂ��Ă͂܂����@�I�ɏ\���ȉ�͂���s���Ă��Ȃ��̂�����ł��B�낤�҂̎�b�ɂ��Ă͌��������g�̏�Q�҃��n�r���e�[�V�����Z���^�[�Ńf�[�^�x�[�X�����i�߂��Ă���A���㕶�@��͂ɗ��p����Ă������̂Ɗ��҂���܂��B
�@�}�ɂ������Ă���܂����A����҂̑����͌y�x�̎��o�E���o�E���̏�Q�҂ł��B����������ƁA���ݑ����Ŋ��Ă���Ⴂ�l��������͂قƂ�ǑS�Ă̐l�����̖��ɒ��ʂ��܂��B���ۂƂ��āA�����ȕ�����ǂ�A�M�������������肷��̂�����Ȃ邱�Ƃ͗e�Ղɑz���ł���Ǝv���܂����A�N���b�N�ƃ_�u���N���b�N���g����������A�h���b�O�����肷�邱�Ƃ�����ɂȂ�P�[�X�����Ȃ葽���A����ɂǂ��Ώ����Ă��������V�X�e���v�҂��\�ߍl���Ă����āA�V�X�e����v���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�܂��B�s�̂̃p�\�R���ł��N���b�N�̃^�C�~���O�𗘗p�҂̍D�݂ɍ��킹�Ē��߂ł���@�\���t���Ă��邱�Ƃ͂����m�̕��������Ǝv���܂��B
�@�R���s���[�^���p�҂ł����܂�m��Ȃ������m��܂��A���Ɏs�̂̃R���s���[�^�Ɏ�������Ă���Z�p���炢�����̋@�\���Љ�܂��B�����̎s�̂̃p�\�R���ɂ͏o���Ɂu�g�勾�v�@�\����������Ă��܂��B����̓}�E�X�J�[�\���̋ߖT���f�B�X�v���C��[�Ɋg�債�ĕ\��������̂ł����A����ɃR���g���X�g����������@�\���t���Ă��܂��B�R���g���X�g�̋���͕����̓ǂ݂₷���ɑ傫���e�����Ă��܂��B�b�͎���܂����A�ŋ߂m�s�s�h�R���������Ă���u�炭�炭�z���U�i���m�ɂ�F671i�j�v�͕����̑傫�����傫���Ȃ��Ă��邾���łȂ��A�w�i�F�����S�Ȕ��ɂ��ăR���g���X�g���m�ۂ��Ă���A���ꂪ�����̓ǂ݂₷���ɑ傫���v�����Ă��܂��B
�@���l�ɁA�s�̂̃R���s���[�^�Ɏ�������Ă���@�\�ł����A�}�E�X���g�킸�L�[����ł��낢��Ȃ��Ƃ��ł��邱�Ƃ��m���Ă����ƕ֗��ł��B����́A���b�l�����o��Q�҂ƈꏏ�ɃC���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W��ǂ�A�������쐬�����肵�Ă��钆�Ŋo�������Ƃł����A���i�}�E�X���g����l�ł��A�l�O�ōu�����Ă���Ƃ��̂悤�ɁA�}�E�X���g���ɂ������ɂȂ�ƁA�L�[����̂��肪�������ǂ�������܂��B�u���̏ꍇ�A�ŋ߂ł̓p���[�|�C���g�i���m�ɂ́AMicrosoft
Power Point�j���g�����Ƃ������Ǝv���܂����A�\�����������e����ʂ����ς��ɕ\������u�X���C�h�V���[�v�ɐ�ւ��邽�߁A���ɂ������Ƀ}�E�X�Ńv���_�E�����j���[���J������A�X���C�h�V���[�̃A�C�R�����N���b�N�����肷��̂�ǂ��������܂��B�������A�X���C�h�V���[�ւ̐ؑւ́uAlt�{V�AW�v�ʼn\�ł����A�X���C�h�V���[�̏I���́u�E�N���b�N�AS�v�ʼn\�ł��B�܂��A�E�B���h�E�����Ƃ������������E��[��X�}�[�N���N���b�N������A�uAlt+F4�v����͂������������̂͊m���ł��B
�@�ȏ�A���ʂ̐l�ł��A�N�Z�V�r���e�B��ł��낢��ȉ��b�ɗ������Ƃ��ł��邱�Ƃ��q�ׂ܂������A�d�x�̏�Q�җp�ɂ͂���ȊO�ɂ��낢��ȍH�v���K�v�ŁA�{�^����ŔC�ӂ̕�������͂���V�X�e����A�g�̉��ɂ���e���r�A�d�b�A�x�b�h�Ȃǂ𐧌䂷�邽�߂̋@�킪�J������Ă��܂��B
�@�܂��ŋ߃R���s���[�^�ƊE�Œ��ڂ���Ă�����̂Ƃ��āA�A�����J�̃��n�r���e�[�V�����@�T�O�W�����j����܂��B����̓A�����J���{�̎x�����Ă���S�Ă̋@�ւŐV���ɃR���s���[�^���w������ꍇ�A���̐E��ɏ�Q�҂����邢�Ȃ��ɂ�����炸�A�K���A�N�Z�V�r���e�B����{�����@���I�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������̂ł��B�A�����J�ł͊��Ɉ��ȏ�̑傫���̃e���r�S�ĂɁA�N���[�Y�h�L���v�V�����i�����p�����j��\������@�\������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��@��������Ă���A����ɑ����[�u�ƌ����܂��B�N���[�Y�h�L���v�V�����\���@�\�ɂ��ẮA�������o��Q�җp�Ƃ��Đv����܂������A��p��b�҂⍂��҂𒆐S�ɗ\�z�ȏ�̗��p�҂̐L�т������Ă��܂��B��L�̃L�[����̂��ƂƓ��l�A�I�������������Ƃ͈�ʗ��p�҂ɂƂ��Ă��֗��Ȃ��Ƃ̂͂��ł��B
�i���F�@�������ɂ��Ă��i���j���[�f�B�b�g�������ɂȂ�ꂽ�y�[�W����ώQ�l�ɂȂ�܂��̂ŁA����������Q�Ɖ������B�j
�@�d�g��ԊO�����g���Ď��o��Q�҂Ɍ��݈ʒu��ڕW���̕�����m�点��u���ē��V�X�e���v���e�n�ł��낢��Ȍ`�ŗ��p����n�߂Ă��܂��B�����̓��ē��V�X�e���̒��ɂ́A��r�I�ア�d�g���o���Ă��锭�M�@�̂��ɍs���Ǝ�M�@���特���K�C�_���X���������Ă���w�����̂Ȃ��V�X�e���ƁA�ԊO���M���Ă��鑗�M�@�Ɏ�M�@��������Ɖ����K�C�h����������w�����̂���V�X�e��������܂��B�O�҂͎w�������Ȃ����߁A�ǂ���ɖڕW�������邩�𐳊m�Ɏ������Ƃ͂ł��܂��A��M�@�������Ă���Ύ����I�ɉ����K�C�_���X���������Ă��܂��B����ɑ��āA��҂͎w���������邽�߁A�����Ŏ�M�@�M�@�Ɍ����Ȃ���Ή����K�C�_���X���������Ă��܂��A�ڕW���̕��������m�ɕ�����̂ŁA�g�C���̓�����Ȃǂ𐳊m�Ɏ������Ƃ��ł��܂��B�܂��A�g�C���̒��ł͔��M�@�ɑ��ĉ��x�̕����ɉ������邩�i�Ⴆ�u�X���̕����ɐ��ʑ䂪����܂��B�v�Ȃǁj�̂悤�ɋ�̓I�ȕ������������Ƃ��ł��܂��B
�@�u���ē��V�X�e���v�ɂ͌���ňē�����V�X�e���ȊO�ɁA�o������O�ɂǂ̉w�łǂ���芷����ΖړI�̉w�܂ŃG���x�[�^�[��G�X�J���[�^�[�����܂��g���ăX���[�Y�ɓ����ł��邩���ē�����V�X�e��������܂��B����҂≺����Q�҂̏ꍇ�A�K�i�̏���~�肪�ł��Ȃ�������A�G�X�J���[�^�[���g���Ȃ�������ƁA���ʂ̐l�ɂ͑z���ł��ɂ����ړ��̏�Q������������܂��B���̂��߁A����z�[���ł̏�芷����G���x�[�^�[�ݒu�w�ł̏�芷����D��I�Ɉē�������V�X�e�����K�v�ɂȂ�܂��B���̂悤�Ȋϓ_�����{������̐��b�l����́u����ҁE��Q�җp�S���œK�o�H�ē��V�X�e���v�����삵�܂����B���b�l���J�������V�X�e���͎���V�X�e���Ō��݈�ʂ̐l�����p���邱�Ƃ͂ł��܂��A��ʃG�R���W�[�E���r���e�B���c���C���^�[�l�b�g��Œ��Ă���u�炭�炭���ł����l�b�g�v�͊T�O�I�ɏ�L�̃V�X�e���ɋɂ߂ċ߂����̂ŁA���S���K�͂ŏ����W������Ă��āA�F�l�����ڂ��g���ɂȂ�܂��̂ŁA�����x�������������B
�@��L�V�X�e���͒P�ɍœK�抷�w���ē����邾���ł������A�w�\���ł̈ړ��o�H����̓I�Ɏ�������A����ɂ̓��@�[�`�������A���e�B���g���āA�ǂ������ڈ�̂Ƃ���łǂ���ɋȂ���Ηǂ����Ȃǂ��A�Տꊴ�̂���摜�ňē����邱�Ƃ��߂������\�ɂȂ���̂Ǝv���܂��B
(5) �����p��J�^���O�u������E�F�u�v�ȂǓd�q��w���E�J�^���O
�@�d�q����������ڂ���Ă��܂����A���ʑ��i��̍ł����ł���A���������p�҂̑������ړ�������ł��镟���p��́A�d�q������ɍł��K�������i���ƍl�����܂��B���̓_�ɒ��ڂ��ĕ����p��̏����C���^�[�l�b�g��ł܂Ƃ߂����̂��u������Web�v�ł��B������Web�͂P�X�X�T�N�����A�h�a�l�̂r�m�r�Z���^�[�i���F�{���́u�X�y�V�����j�[�Y�V�X�e���Z���^�[�v�̗����ł����A�����̐ӔC�҂ł������֍�����l�i���A�i���j���[�f�B�b�g��\������В��j�́u��Q�҂Ȃ�ł����k�Z���^�[�v�̗������ƌ����Ă���Ə��Ă��������ꂽ�̂���ۓI�ł��B�j���J�݂������̂ł����A���݂�JEIDA�i�Ёj�d�q���Z�p�Y�Ƌ���Ǘ����Ă��܂��B������Web�ɂ͐����S�ʂɂ킽���Ă��낢��ȕ����p��̏�ڂ��Ă��܂��̂ŁA�����x�`���Ă݂ĉ������B
�@�����p����u���i�v�Ƃ����ϓ_���猩���ꍇ�A�u���i�Љ�v�ƕ���ŏd�v�Ȃ̂��u���p�҈ӌ��̃t�B�[�h�o�b�N�v�ł��B�{������̐��b�l����̑̌��k���猾���ƁA�����p��͗��p�҂���̃t�B�[�h�o�b�N���قƂ�ǂȂ����߁A���p�҂̃j�[�Y���炩�����ꂽ���i�����C�Ŕ����Ă��܂��B
�@���b�l����́u�G���{�[�N���b�`�v�i���F�I���t���^�x���Ŏx���A�n���h������ň���^�C�v�̏�j���g���Ă��܂����A�G���{�[�N���b�`�ɂ����X�̖��_������܂��B���݁A�h�r�n�ō��ۋK�i����낤�Ƃ��Ă��܂����A���̒��Łu����Ȃ��Œ������߂��s���邱�Ɓv�����L����悤�Ƃ��Ă��܂��B���b�l����͌��ݓ��{���N�����p��H�Ɖ�̃G���{�[�N���b�`���ۋK�i�K�����ψ���̈ψ������Ă���A�����Ŕ��Έӌ��������Ă��܂����A��̒������ߋ@�\�͒����Ԏg���������ꍇ�A�u�K�^�v�̌����ƂȂ�A���Ԃ��o�ɂ�āA�������тɃJ�`�J�`�������錴���ƂȂ�܂��B�������̎q���ȊO�̐��l�ɂƂ��ẮA�������߂͍w�����Ɉ�x��������Ηǂ����ƂŁA�Ȍ�S���s�v�ȋ@�\�ł��B����Ȃ��Œ������߂��\�ȏ�����I�Ɏg�����Ƃ́u���D���̎���t�����܂܂ŕ��𒅂�v�ƌ����Ă���̂ƑS�������ł��B
�@���l�Ɋ��҂̐������Ȃ��a�C��A��r�I�ŋߖ��炩�ɂȂ����a�C�ɂ��Ă̏��͂Ȃ��Ȃ����҂̎茳�ɓ͂��Ă��܂���B���̂悤�ȏꍇ�ɂ��a�C�Ɋւ���ŐV�̒m�������҂̎茳�ɂ��������͂��邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂��B
(6) �d�q���N�蒠�A�d�q�g�̏�Q�Ҏ蒠�A�h�b�J�[�h�}���^�V���o�[�V�[�g�Ȃǂ̗D��T�[�r�X�x���E���N�Ǘ��c�[��
�@�ȏ�̂T���ڂ͂���������݉��炩�̌`�ŋZ�p����������Ă�����̂ł����A���̍��͐�[�Z�p�̕����ւ̉��p��V���ɒ�Ă�����̂ł��B
�@���̂P�́u�d�q���N�蒠�v���邢�́u�d�q�g�̏�Q�Ҏ蒠�v�Ƃ����l�����ł��B���ʂ̐l�ł��u�����̌��N�Ɋւ���f�[�^���P���̃J�[�h�ɋL������Ă��āA���߂Ă̕a�@�ɍs���Ă������ɍs���t���̕a�@�̂悤�Ɏ����̂��Ƃ�����������ǂ�Ȃɕ֗����낤�B�v�Ǝv�������Ƃ͂Ȃ��ł��傤���H�����I�ɃJ���e�͕a�@�ɋA�����邽�߁A�]�����ŐV�����a�@�ɂ�����Ƃ��ɂ͂w���ʐ^�ȂǑS�Ẵf�[�^����蒼���ɂȂ�܂��B�܂��A�{�l�ł��ߋ��̕a���̋L���������܂��ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂����A�ˑR����œ|�ꂽ�悤�ȏꍇ�ɂ͕a���̐�������ł��܂���B����ɁA�����̕a�C�ŕ����̉Ȃ�a�@�ɂ������Ă���ꍇ�������Ǝv���܂����A��̕������^�͎v��ʎ��̂������܂�����A�a���A��������ꌳ�I�ɊǗ����邱�Ƃɂ͑傫�ȃ����b�g������܂��B
�@�ȏ�̂悤�ȗ��R���獑���S�ĂɁu�d�q���N�蒠�v���邢�́u���N�L�^�J�[�h�v�Ƃ������h�b�J�[�h��z�z���A��Q�҂͂���ɏ�Q�̃f�[�^���L�������āu�d�q�g�̏�Q�Ҏ蒠�v�ɂ�����ǂ��Ǝv���܂��B
�@���݈���łh�s�r�i���x��ʃV�X�e���j�ɂ�����d�s�b�i������������j�V�X�e���̂悤�ɁA�Ԃ��~�߂Ȃ��Ă������x�������ł���Ƃ����̂ɁA��Q�җp�̒��ԏ�ɂ͌��݂ł��Ԃ��R�[���i�~����̏�Q���j�Ȃǂ��u����A�g�p���ɂ͏�Q�҂����̃R�[�������Ȃ���Β��ԏꂪ���p�ł��Ȃ��Ƃ����������N�����Ă��܂��B��L�́u�d�q�g�̏�Q�Ҏ蒠�v���������A�o�[�������I�ɊJ���A���ԏꂪ�g����悤�ɂ��邱�Ƃ͋Z�p�I�ɏ\���\�Ȃ͂��ł��B
�@�܂��A�u�d�q�g�̏�Q�Ҏ蒠�v�͓d�Ԃ́u�D��ȁv�ȂǁA���낢��ȂƂ���ŗ��p�\�ł��B�u�d�q�g�̏�Q�Ҏ蒠�v���������܂Ȃ��ƗD��Ȃ̈֎q������Ă��Ȃ��悤�ɂ���A�Ώێ҂Ƃ���ȊO�������ɕ�����܂��B���������Ȃǂ̗��R�ŗD��Ȃ𗘗p����ꍇ�A��������A���ʂ̐l�ƌ��������t���Ȃ����߁A�����̐l���D��Ȃ𗘗p���Ă��Ă���ʂ̐l���甒���ڂŌ����A���g�̋����v�������Ă��܂��B�������A�u�d�q�g�̏�Q�Ҏ蒠�v������ΒN�ɂ͂��邱�Ƃ��Ȃ��A�D��Ȃ𗘗p���邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�܂��A������Q�҂ɂ͗L�����H�̊��������z���Ă��āA���̊������̕s���g�p�i�s�����n�ɂ�鑼�l�g�p�j�����ɂȂ��Ă��܂��B�u�d�q�g�̏�Q�Ҏ蒠�v�ڗ������Œ���悤�ɂ���A�������̕s���g�p���ꋓ�ɂȂ��Ȃ�܂��B
�@�����ł́u�d�q�g�̏�Q�Ҏ蒠�v���Ɏ����܂������A���l�ɐ�[�Z�p�ŕ����ɉ��p�ł�����̂͐���������Ǝv���܂��B����܂ŋ@�B�H�w�����S�ł������Q���Y�ƓI�ȕ����H�w�̕���ɂh�s�Z�p���g�����R���Y�ƓI�ȐV�����̈���J�Ă����Ȃ�������Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�o���A�t���[���C�t�Z�p������̃g�b�v�y�[�W�ɖ߂�
Go back to the top page of this site