
このページは第16回リハビリテーション工学カンファレンス(2001年8月27〜29日にママカリフォーラム岡山にて開催)で発表した内容をhtml形式で記述したものです。講演論文集に掲載されている原稿のpdfファイルも別途用意してあります。
1.はじめに
2.システムの特長
3.バリアフリーな入出力インタフェース
4.利用者の身体的条件を考慮した経路案内
4−1.乗り換え経路探索
4−2.乗り換え時間の算出
4−3.最適経路の抽出例
5.おわりに
参考文献
現在、鉄道で目的地まで到達するための最適経路を自動的に案内する市販のプログラムやインターネットのサイトが多数ある。これらのプログラムにおいては乗車時間だけでなく、乗換駅での移動距離や運転間隔の情報を利用して乗り換え時間をも含め高い精度の計算をしており、利用者にとっては極めて利用価値が高い。ところが、これらの鉄道最適経路案内システムは、あらゆる設備が容易に利用できる健常者を前提に作られており、高齢者や障害者のように、階段やエスカレーターなどが使えない場合には、案内された経路が必ずしも最適になっていないことがある。例えば、乗車時間は短いが乗換駅にエレベーターが設置されていない経路Aよりも、乗車時間は長くても乗換駅にエレベーターが設置されている経路Bの方が、結果的に合計の所要時間が短くなるケースがある。
この種の案内システムは、移動が困難で事前情報を必要としていながら、それらの情報が得にくい高齢者や障害者にとってこそ有効であるべきであり、利用者の身体的条件の考慮が必須なはずである。折りしも昨年11月に交通バリアフリー法が施行され、徐々にではあるがエレベーター設置駅が増えつつある状況の中で、実際にそこに行くことが困難な高齢者や障害者にはそこに設置されたという情報すらなかなか入ってこない。
このような観点から筆者らは通信・放送機構(TAO)の高齢者・障害者向け通信・放送サービス充実研究開発助成金を得て、バリアフリーなコミュニケーション手段を用い、高齢者・障害者に適した鉄道最適経路案内システムを試作したので、その概要を報告する。
本システムには
(1) バリアフリーな入出力インタフェース
乗車区間や身体的条件を利用者の音声で認識し、乗り換え経路や駅構内の情報を音声ガイダンスと文字情報で提供する。
(2) 利用者の身体的条件を考慮した経路案内
階段およびエスカレーターの利用可否、歩行および階段昇降の速さなどを考慮してその利用者独自の乗り換え時間を算出し、全行程の所要時間を求めて、短い順に複数の経路を案内する。
の2つの特長がある。
情報の入出力は現在のところ携帯電話を含む電話を用いているが、携帯電話に関しては近い将来音声の入出力と画像表示を同時に行う機能が付加されるために、その時点では詳細情報を音声ガイダンスとテキスト表示で同時に提供できる。(現在のところ、まだ携帯電話での同時表示が技術的に不可能であるため、電話から音声ガイダンスが流れ、テキスト情報がデモ・システムのディスプレイ上に表示されている。)
入力する情報は乗車区間と身体的条件であり、乗車区間は乗車駅と降車駅の駅名を入力する。一方、身体的条件は表1に示す4項目を音声ガイダンスとの対話形式で入力する。なお、当社で開発した音声認識システムでは音声入力の途中で「えーと」や「あのー」などの不要な語が入ってもそれらを無視する機能を有している(1)。また音声ガイダンスが聞き取りにくい場合には「もう一度」、「もっとゆっくり」、「もっと大きく」などのコマンドも受け付け、それに応じて音声出力の速度や音量を調節する機能も有している。
| 入力項目 | 単位 | 備考 |
| 1分当たり水平移動距離 h | m | |
| 1分当たり上り階段移動段数 u | 段 | 「0」は階段利用不可を意味する |
| 1分当たり下り階段移動段数 d | 段 | 「0」は階段利用不可を意味する |
| エスカレーター利用可否 e | − | 利用可能なら「1」、不可なら「0」 |
なお、身体的条件については毎回入力することは不要であり、利用者番号(常に特定の電話からしか利用しない場合はナンバー・ディスプレイ機能で通知される発信電話番号)で利用者を特定し、以前に入力した身体的条件を用いる。
結果の出力においては合計の所要時間が短い順に複数の経路の乗換駅の名称と利用線区の名称(快速や各駅停車などの区別がある場合にそれぞれを別の線区として扱う)を案内する。さらにそれぞれの乗換駅と利用線区については利用者からの要求に基づいて表2に示す詳細情報を音声ガイダンスおよびと画面上のテキスト表示で案内する。
| 乗換駅の詳細情報 | ホーム間距離 H(m) 上り階段数 U(段) 下り階段数 D(段) 上りエスカレーターの有無 Eu (あれば「1」、なければ「0」) 下りエスカレーターの有無 Ed (あれば「1」、なければ「0」) エレベーターの有無 El (あれば「1」、なければ「0」) 利用者の身体的条件から計算した乗り換え時間 T(分) |
| 利用線区の詳細情報 | 途中停車駅数 (駅) 所要時間 (分) |
本システムでは各線区の接続情報を接続駅数行列Tで管理しており、これに前後から乗車駅の路線ベクトルSと降車駅の路線ベクトルEを掛け、
P = S・Tn・ET
を計算することで、候補経路数Pを求める。ここで、ETはEの転置行列を表しており、nは乗り換え回数を表している。
本システムでは高齢者・障害者の身体的苦痛を考慮して基本的には乗り換え回数を最小にするアルゴリズムで経路を探索しており、Pを1以上にする最小のnが最小乗り換え回数である。なお、乗り換え回数が多少増えても結果的に所要時間が短くなる場合にはそのような経路を案内することもできるようにするため、乗り換え回数マージンmを設け、最小乗り換え回数よりm回だけ多い乗り換えを行うすべての経路の所要時間を算出し、短いものを上位5位まで求める。
乗り換え回数が多いが、乗車時間が短い経路がある場合には、移動が困難な人ほど4−2.で述べる乗り換え時間が長くなる。このため、乗り換え回数が少ない経路が自動的に選択されて案内され、結果的にそれぞれの利用者の身体的条件にあった経路案内が可能となっている。
乗り換え時間の算出に当たっては先に音声で入力した利用者の身体的条件と各駅(正確には当該駅での各線区のホーム間)の乗り換え経路の情報(表2参照)を利用して乗り換え時間を算定する。乗り換え時間は水平移動時間Th、 上り方向移動時間Tu、 下り方向移動時間Td、平均待ち時間Twの和として定義される。
まず、水平移動時間は各利用者の水平移動速度を考慮して
Th=H/h
として求める。
次に、上り方向移動時間および下り方向移動時間は以下に述べる手順で算出する。
(1) 同一ホームでの乗り換えの場合、
Tu(またはTd)=0
(2) 上りまたは下りエスカレーターが設置されており(EuまたはEd=1)、利用者がエスカレーターを利用可能である(e=1)場合、
TuまたはTd=エスカレーター所要時間
(3) エレベーターが設置されている(El=1)場合、
TuまたはTd
=エレベーター所要時間と
U/uまたはD/dの短い方
(4) エレベーターが設置されておらず(El=0)、利用者が階段を利用できる(dまたはu>0)場合、
TuまたはTd=U/uまたはD/d
(5) エレベーターが設置されておらず(El=0)、利用者が階段を利用できない(dまたはu=0)場合、
TuまたはTd
=駅員等に手伝ってもらう時間
本システムでは上記のエスカレーター所要時間、エレベーター所要時間、駅員等に手伝ってもらう時間をそれぞれ1分、2分、20分とした。
本システムの機能を車椅子利用者を例に紹介する。ただし、首都圏の場合一部併走路線が多く(この例では山手線と京浜東北線、山手線と埼京線)、全駅を乗換候補駅として用いると経路数が膨大になり、理解の妨げになるため、図1に示した簡単化した鉄道網に基づいて大宮から新大久保に至る経路を求めた。

なお、この経路の場合、埼京線を用いて池袋まで行き、山手線の内回りで新大久保まで行くのが通例であるが、
(1) 埼京線が恵比寿まで延長開業し、恵比寿駅にエレベーターが設置されていること、
(2) 田端駅や東京駅では京浜東北線と山手線が同一ホームを利用していること
の2点を知った上で以下の例を見て頂きたい。
4−1.で述べたとおり、まず乗り換え経路をすべて求める。この乗車区間の場合、乗車駅の路線ベクトルS、接続駅数行列Tおよび降車駅の路線ベクトルEはそれぞれ図2に示すとおりである。
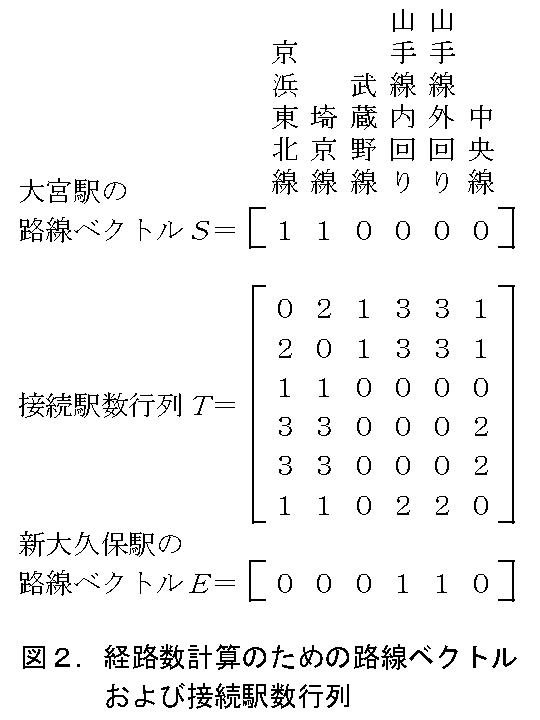
ここで山手線だけは内回りと外回りを別々の線区として扱う。他の線区ではある駅からある駅に至る経路が複数存在するということはないが(快速と各駅停車の場合は元々別の線区と考える)、山手線の場合、両方向の経路を考える必要がある。
まずn=0の場合についてP=S・ETを計算すると0となるから、乗り換えなしでは大宮駅から新大久保駅に至る経路はないことが分かる。
次にn=1の場合についてP=S・T・ETを求めると12であるから、乗換駅および利用線区の選び方によって乗り換え回数1回で到達する経路が12種類あることが分かる。
本システム内では12とおりのすべての経路について所要時間を計算する訳でその結果を表3に示す。まず注目して頂きたいのは通常の池袋乗り換えが4位になっていることである。(注: 現在は池袋駅にもエレベーターが設置されたため、車椅子利用者にとっても池袋乗り換えが最も便利になったが、この原稿発表当時、同駅にはエレベーターが設置されていなかった。)先にも述べたとおり恵比寿駅にエレベーターが設置されたため、いったん池袋・新宿などの各駅を通り過ぎて恵比寿まで行き、山手線の外回りで新大久保まで戻る経路が最も早いことが分かる。2位、3位は京浜東北線から山手線外回りへの同一ホームでの乗り換えである。
| 順位 | 経 路 | 所要時間(分) |
| 1 | 大宮- (埼京線)→恵比寿- (山手線外回り)→新大久保 | 114 |
| 2 | 大宮- (京浜東北線)→東京- (山手線外回り)→新大久保 | 123 |
| 3 | 大宮- (京浜東北線)→田端- (山手線外回り)→新大久保 | 126 |
| 4 | 大宮- (埼京線)→池袋- (山手線内回り)→新大久保 | 131 |
| 5 | 大宮- (埼京線)→新宿- (山手線外回り)→新大久保 | 133 |
| 6 | 大宮- (京浜東北線)→田端- (山手線内回り)→新大久保 | 136 |
| 7 | 大宮- (埼京線)→恵比寿- (山手線内回り)→新大久保 | 154 |
| 8 | 大宮- (京浜東北線)→品川- (山手線外回り)→新大久保 | 157 |
| 9 | 大宮- (京浜東北線)→東京- (山手線内回り)→新大久保 | 161 |
| 10 | 大宮- (京浜東北線)→品川- (山手線内回り)→新大久保 | 177 |
| 11 | 大宮- (埼京線)→池袋- (山手線外回り)→新大久保 | 181 |
| 12 | 大宮- (埼京線)→新宿- (山手線内回り)→新大久保 | 191 |
なお、山手線の内回り利用と外回り利用を、田端乗り換えを例に比較してみる。本来の乗車距離からいえば田端から新大久保までは山手線内回りに乗車する方が近いはずであるが、前述した同一ホームか否かの違いが影響して田端から山手線内回りを利用する経路は136分かかってしまい、外回りを利用する経路より約10分余計にかかることになる。
本システムはTAOの助成金を用いて試作したが、期間および予算の面から最適経路を求めるアルゴリズムの実装に重点が置かれ、データはアルゴリズムの正当性を検証するために投入されたJRの東京都および埼玉県内の各線だけである。このため、少なくとも首都圏全域に拡張すべくデータの拡充に努力したいと考えている。
案内対象を東京都と埼玉県内のJR各線に限定しているものの、エスカレーターや階段が利用できない高齢者や障害者の身体的条件を考慮し、さらに入力の容易な音声認識を利用した鉄道最適経路案内システムを通信・放送機構(TAO)の高齢者・障害者向け通信・放送サービス充実研究開発助成金を得て試作した。
徐々に各駅にエレベーターが設置されることは非常に好ましいことであるが、目を海外に転ずると自転車を電車内に持ち込める国もある。高齢者がセニアカーで電車内まで乗り込め、目的地でも地元と同じ快適さが楽しめるような環境を作るのも技術的は夢ではないはずだ。来るべき高齢社会に向けて、今何ができるかを一人一人が真剣に考えなければいけない時期に来ていると思う。
| (1) | 黒岩眞吾:“特集−’99音声認識探検隊−通信サービスにどう応用できるか?(KDD)”, エレクトロニクス1999年8月号, pp. 59-62 (1999). |