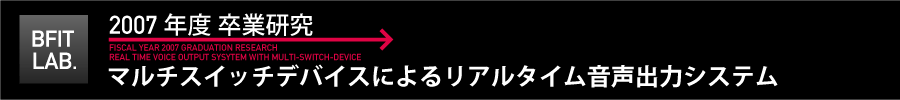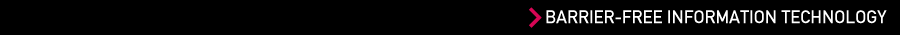デモンストレーション
下の画像をクリックすると、製作したデバイスのデモンストレーションが再生できます。(※IEのみ対応)
考察
製作したデバイスを使用するにあたって、主観的評価であるが次のようなことが言えます。
話し相手に注意して聞いてもらえれば、意思の疎通を行うことができました。ただし、他人の会話に割って入るようなことは難しいのが現状です。1対1で会話することは可能であると思われるますが、多人数での会話に使用するためには、いくらかの改良が必要でしょう。
また、出力する文字によっては、聞き取りづらく聞きまちがいが多いということがありました。
ほかにも、ユーザが押しているつもりでも、プログラムでは認識されていないことが、かなりの頻度で起きるという問題が見受けられました。
これからの開発にあたって
最大の課題が、デバイスの小型化です。本研究で製作したプロトタイプは、とてもウェアラブルとは言えないサイズです。携帯することも難しいでしょう。今後、デバイスをどのようにして小さくするかが必須項目となります。
次にユーザの使用感の向上。ボタンの押しやすくすることや、認識精度の向上などが必要です。
様々なボタンスイッチを使ってデバイスを試作したり、認識部の状態遷移などを改良することによって、問題を解決できると考えられます。
今後は、長松氏の研究分野であるユーザとのインターフェースやアクセントの付与など、機能の追加なども求められるでしょう。

下の画像をクリックすると、製作したデバイスのデモンストレーションが再生できます。(※IEのみ対応)
考察
製作したデバイスを使用するにあたって、主観的評価であるが次のようなことが言えます。
話し相手に注意して聞いてもらえれば、意思の疎通を行うことができました。ただし、他人の会話に割って入るようなことは難しいのが現状です。1対1で会話することは可能であると思われるますが、多人数での会話に使用するためには、いくらかの改良が必要でしょう。
また、出力する文字によっては、聞き取りづらく聞きまちがいが多いということがありました。
ほかにも、ユーザが押しているつもりでも、プログラムでは認識されていないことが、かなりの頻度で起きるという問題が見受けられました。
これからの開発にあたって
最大の課題が、デバイスの小型化です。本研究で製作したプロトタイプは、とてもウェアラブルとは言えないサイズです。携帯することも難しいでしょう。今後、デバイスをどのようにして小さくするかが必須項目となります。
次にユーザの使用感の向上。ボタンの押しやすくすることや、認識精度の向上などが必要です。
様々なボタンスイッチを使ってデバイスを試作したり、認識部の状態遷移などを改良することによって、問題を解決できると考えられます。
今後は、長松氏の研究分野であるユーザとのインターフェースやアクセントの付与など、機能の追加なども求められるでしょう。